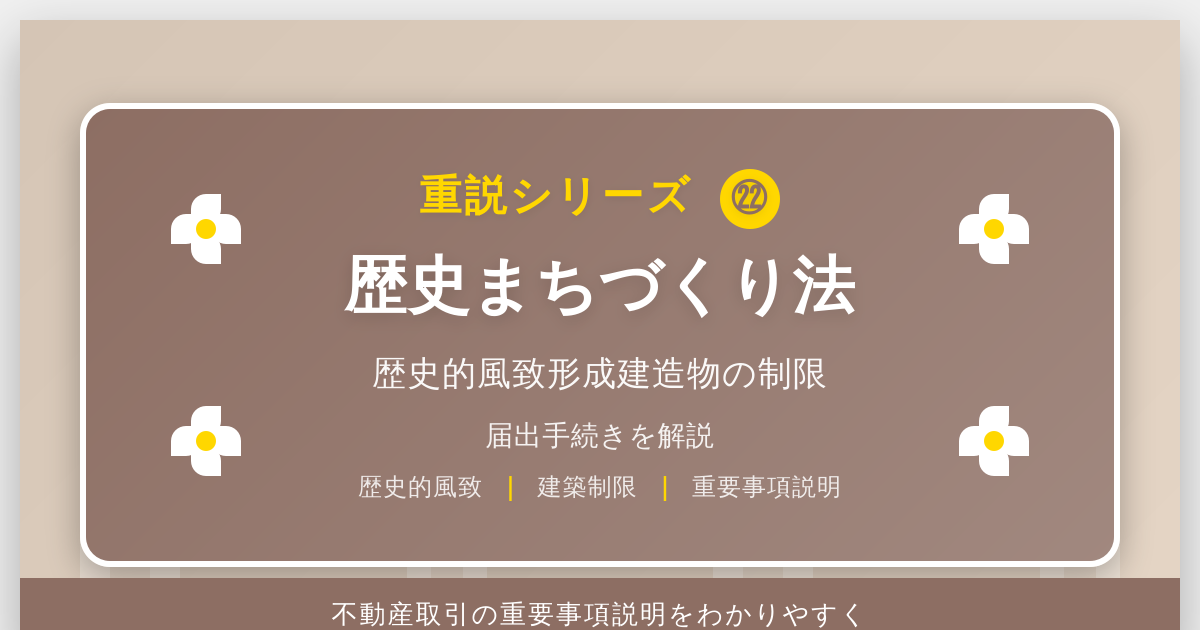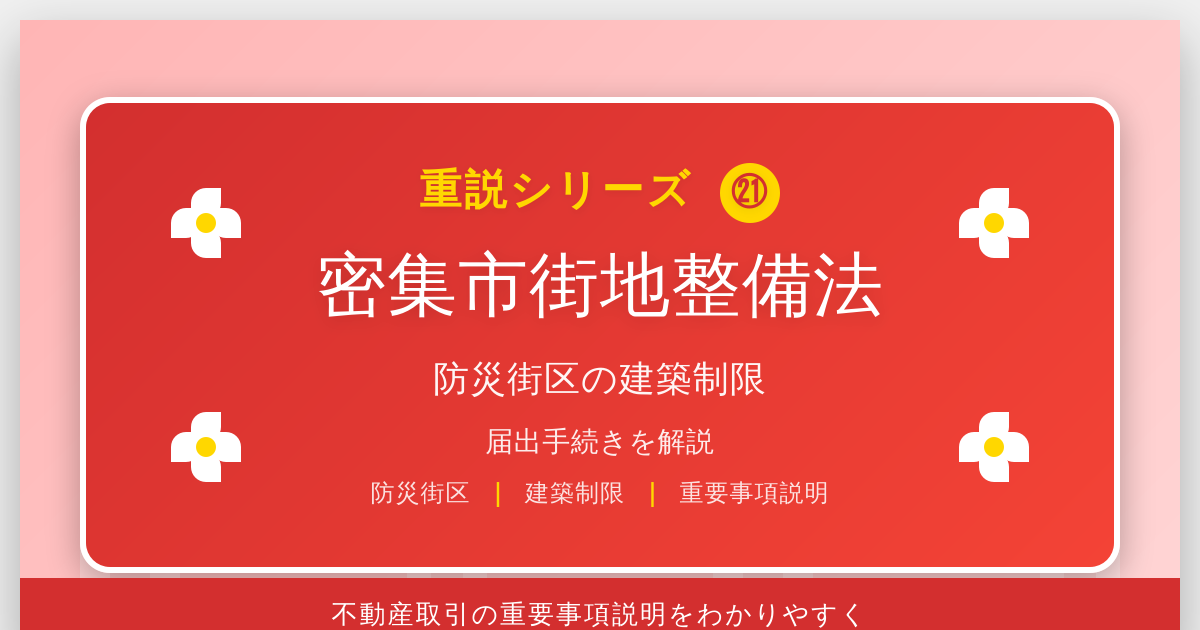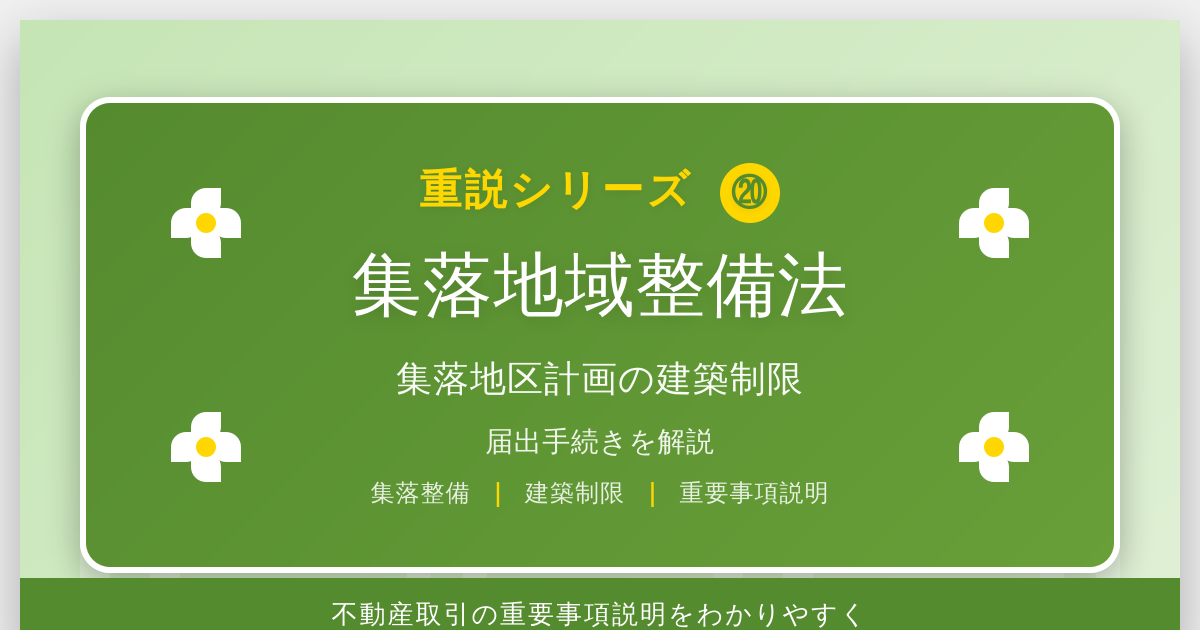被災市街地復興特別措置法とは?「復興推進地域」の建築制限を解説|重説シリーズ⑪
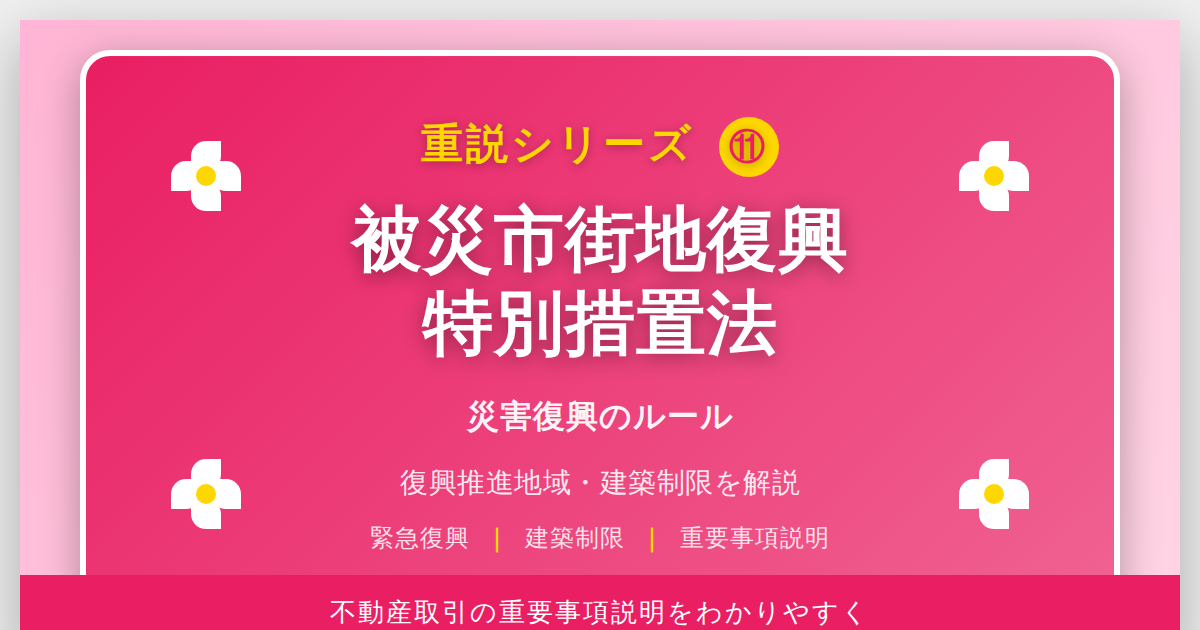
被災市街地復興特別措置法の「復興推進地域」と建築制限を徹底解説。災害後の市街地復興に必要な建築制限の仕組み、指定要件、重要事項説明のポイントを初心者にもわかりやすく図解します。
📑 目次
被災市街地復興特別措置法とは?「復興推進地域」の建築制限を解説|重説シリーズ⑪
❓ 大規模な災害(地震や津波)にあった街の再開発って、どうやるの?
❓ 「被災市街地復興推進地域」に指定されると、家は建てられない?
❓ この法律、東日本大震災や能登半島地震と関係ある?
この法律は、阪神・淡路大震災を教訓に制定された法律で、地震や津波などで壊滅的な被害を受けた市街地を、「迅速かつ健全に」復興させるための特別なルールを定めています。不動産取引では、復興計画が決まるまでの間、無秩序な建築を一時的にストップさせる建築制限(法第7条)が最重要ポイントとなります。
🕊️ 法律の目的と役割:迅速かつ健全な復興
この法律の正式名称は「被災市街地復興特別措置法」です。1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災の直後に制定されました。
あの大震災では、多くの建物が倒壊・焼失しました。しかし、すぐに復興事業(区画整理など)を始めようにも、通常の都市計画法の手続きでは時間がかかりすぎます。その間に、被災した方々が生活再建のためにバラバラに建物を建て直してしまう(=無秩序な再建)と、将来の防災性の高い街づくり(広い道路や公園の確保)が不可能になってしまいます。
そこで、この法律は、通常の都市計画法や土地区画整理法の手続きを大幅に短縮・簡略化する**「特例措置」**を設け、復興事業をスピードアップさせることを目的としています。
被災市街地復興法の主な目的
- 迅速な復興: 通常の法律(都市計画法など)の複雑な手続きを簡略化し、復興事業をスピードアップさせます。
- 健全な復興: バラバラな再建を防ぎ、道路や公園を確保した、防災性の高い安全な街づくりを誘導します。
(図解:無秩序な再建を防ぎ、計画的な復興へ誘導する)
🏛️ 重説の最重要ポイント「被災市街地復興推進地域」(法第7条)
不動産取引において、この法律で最も重要になるのが**「被災市街地復興推進地域」**の指定です。
これは、大規模な災害により市街地が大きな被害を受けた場合に、都市計画で指定されるエリアです。この指定の目的は、**「復興計画(土地区画整理など)が決定するまでの間、無秩序な建築を一時的にストップさせる」**ことにあります。
建築行為等の制限(法第7条1項)
「被災市街地復興推進地域」が都市計画決定されると、その区域内では、復興事業の障害となる行為が厳しく制限されます。
この区域内で以下の行為をしようとする者は、原則として**都道府県知事等の「許可」**が必要になります。
⚠️ 知事の「許可」が必要な行為(法7条)
- 土地の形質の変更(切土、盛土、造成など)
- 建築物・工作物の新築、改築、増築
※これは「土地区画整理法76条許可」とほぼ同じ内容です。復興計画の妨げになると判断されると、建築は許可されません。
制限がかかる期間は?
この建築制限は、復興事業が始まるまで延々と続くわけではありません。この法律は「迅速な復興」が目的なので、制限期間は厳格に定められています。
- 制限の開始: 「被災市街地復興推進地域」が都市計画決定された日から。
- 制限の終了: 原則として、**災害発生日から起算して「2年」**以内。
この2年間は、行政が復興計画を立てるための「待った」の期間です。この期間内に土地区画整理事業などが決定されれば、この法律(法7条)の制限は解除され、次のステップである「土地区画整理法76条」などの事業固有の制限にバトンタッチされます。
🚀 復興を加速させるための「特例措置」
この法律の真価は、復興事業の手続きを大幅にスピードアップさせる「特例」にあります。通常なら数年かかる手続きを数ヶ月に短縮することで、早期の復興を目指します。
(図解:通常の開発と被災市街地復興事業のスピードの違い)
主な特例措置には以下のようなものがあります。
- 都市計画決定の特例:通常は別々に行う「都市計画決定」と「事業認可」の手続きを、同時に(一体的に)行うことができます。これにより、事業開始までの期間が劇的に短縮されます。
- 土地区画整理事業の特例(被災市街地復興土地区画整理事業):通常の区画整理よりも、同意が必要な人数(施行要件)が緩和され、よりスピーディに事業を開始できます。
- 市街地再開発事業の特例(被災市街地復興市街地再開発事業):防災性の高い共同住宅(復興ビル)を建てる際の手続きが簡略化されます。
- 建築基準法の特例:集団移転先での建築規制の緩和など、被災者の迅速な住宅再建を後押しするルールが適用されます。
✅ 重要事項説明での扱いとチェックポイント
取引する土地が「被災市街地復興推進地域」内にある場合、宅地建物取引業者はその内容を重要事項説明(重説)で買主に説明する義務があります。
1. 重説で説明される項目
重説では、主に以下の点が説明されます。
- 法律名: 被災市街地復興特別措置法 第7条1項
- 区域の指定: 当該土地が「被災市街地復興推進地域」内にある旨。
- 制限の概要: 建築物の新築・改築・増築や土地の形質の変更には、**都道府県知事等の「許可」**が必要であること。
- 制限の期間: この制限がいつまで続くのか(原則、災害発生日から2年以内)の説明。
2. 買主・仲介業者のチェックポイント
新人営業マンや買主様は、特に以下の点に注意して確認しましょう。
被災市街地復興法 取引チェックポイント
- ① 「推進地域」に指定されているか?
大規模災害があった地域では、まずこの区域に指定されていないかを行政(都市計画課など)に確認することがスタートラインです。 - ② 制限期間はいつまでか?
法7条の制限は「災害発生日から最大2年」の時限措置です。この2年の間に復興計画が決まらなければ、制限は解除されます。逆に、期間内に次の事業(土地区画整理など)が決まれば、そちらの制限(例:76条許可)に引き継がれます。 - ③ 建築許可の見込みは?
この期間中にどうしても建築したい場合、「復興計画の妨げにならない」と判断されれば許可が下りる可能性もありますが、原則として難しい(復興計画が決まるまで待つ)と考えるべきです。 - ④ 将来の街区はどうなるか?
この指定がされているということは、近い将来、土地区画整理事業などによって道路が広くなったり、土地の場所(換地)が変わったりする可能性が極めて高いことを意味します。
❓ FAQ(よくある質問と回答)
Q1: この法律は、東日本大震災や能登半島地震でも使われましたか?
A1: はい、使われました。東日本大震災では、津波で甚大な被害を受けた多くの沿岸市街地で「被災市街地復興推進地域」が指定され、その後の高台移転や土地区画整理事業がこの法律の特例措置によって迅速に進められました。2024年の能登半島地震においても、輪島市などでこの法律に基づく復興計画が進められています。
Q2: 制限期間(災害発生から2年)が過ぎたらどうなりますか?
A2: 2年以内に次の復興事業(土地区画整理事業など)が都市計画決定された場合、法7条の制限は終了し、土地区画整理法76条などの「事業固有の制限」に切り替わります。もし2年以内に何も決まらなかった場合は、法7条の建築制限は自動的に解除され、建築が可能になります。
Q3: 区域内で、被災した家をリフォームするのはダメですか?
A3: 「改築」や「増築」は許可の対象です。ただし、災害からの復旧のための応急措置(ブルーシートをかける、壁の穴をふさぐ等)や、通常の管理行為(軽微な修繕)は許可不要とされています。大規模なリフォームやリノベーションは「改築」にあたる可能性があるため、必ず行政に確認が必要です。
Q4: 法7条の建築許可は簡単に下りますか?
A4: 非常に厳しいです。この制限の目的は「復興計画が決まるまで建築を待ってもらう」ことだからです。復興計画(新しい道路計画など)の妨げにならないことが明らかな場合や、被災者のための仮設住宅など、公益性が高いもの以外は、許可が下りるのは難しいと考えられます。
Q5: 「被災市街地復興土地区画整理事業」とは何ですか?
A5: この法律の特例を使って行われる、スピード重視の土地区画整理事業です。通常の土地区画整理事業よりも、事業開始に必要な同意者の数が少なく(過半数の同意でOKなど)、手続きも簡略化されているため、迅速に街の区画を整備し直すことができます。
まとめ
「被災市街地復興特別措置法」は、大災害からの復興という緊急事態において、都市計画を迅速に進めるための法律です。不動産取引では、復興計画の策定中にかかる一時的な建築制限が重要です。
🔑 被災市街地復興法における重要ポイント
- 大災害からの「迅速かつ健全な」復興を目的とした時限的な法律です。
- 重説の対象は**「被災市街地復興推進地域」**の指定です。
- この区域内では、災害発生から最大2年間、建築や造成に知事等の「許可」が必要です。
- この制限は、土地区画整理事業などの本格的な復興事業が始まるまでの「つなぎ」の制限です。
売買・仲介に携わる宅地建物取引業者は、被災地での取引において、この一時的な建築制限がかかっていないか、かかっている場合はいつまで続くのか、そして将来どのような街づくり計画が進められているのかを正確に調査し、説明する責任があります。
ご不安な不動産取引はオッティモにご相談ください
被災地の不動産売買や、復興事業区域内の法令上の制限についてご不明な点がございましたら、不動産取引の専門家であるオッティモが承ります。お気軽にご連絡ください。
📞 電話で相談 (03-4503-6565) 💬 LINEで相談 (@466ktyjp) 💻 チャットで相談営業時間: 平日9:00〜18:00
❓ よくある質問(FAQ)
空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:
- 登記済権利証または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- 建物の図面や測量図
- 身分証明書
査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。