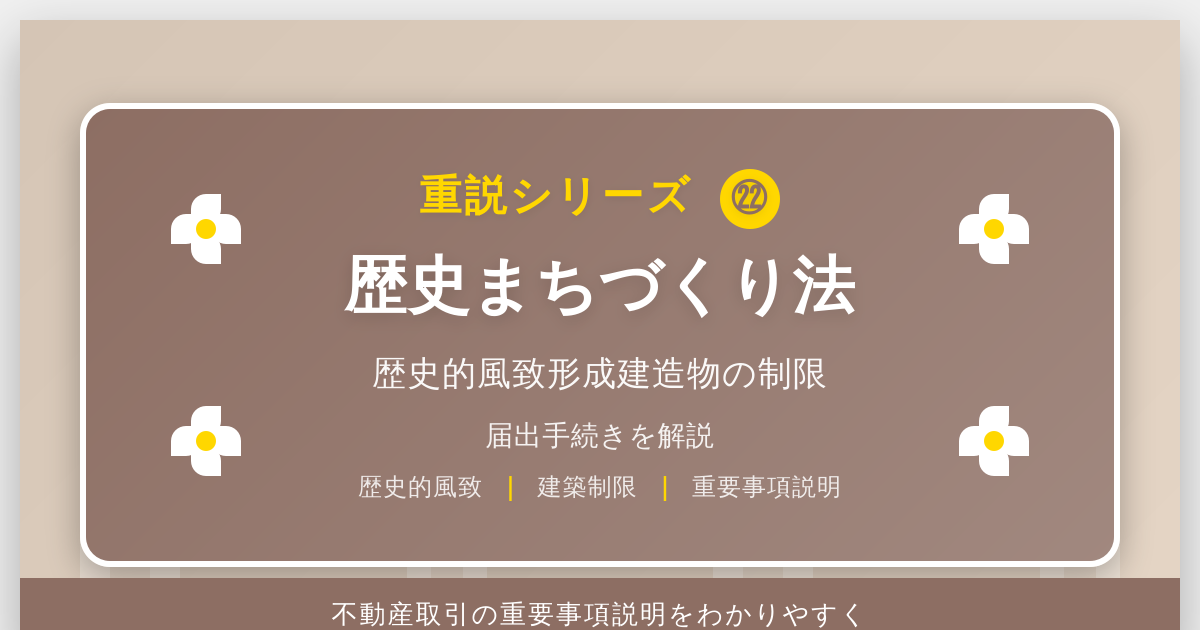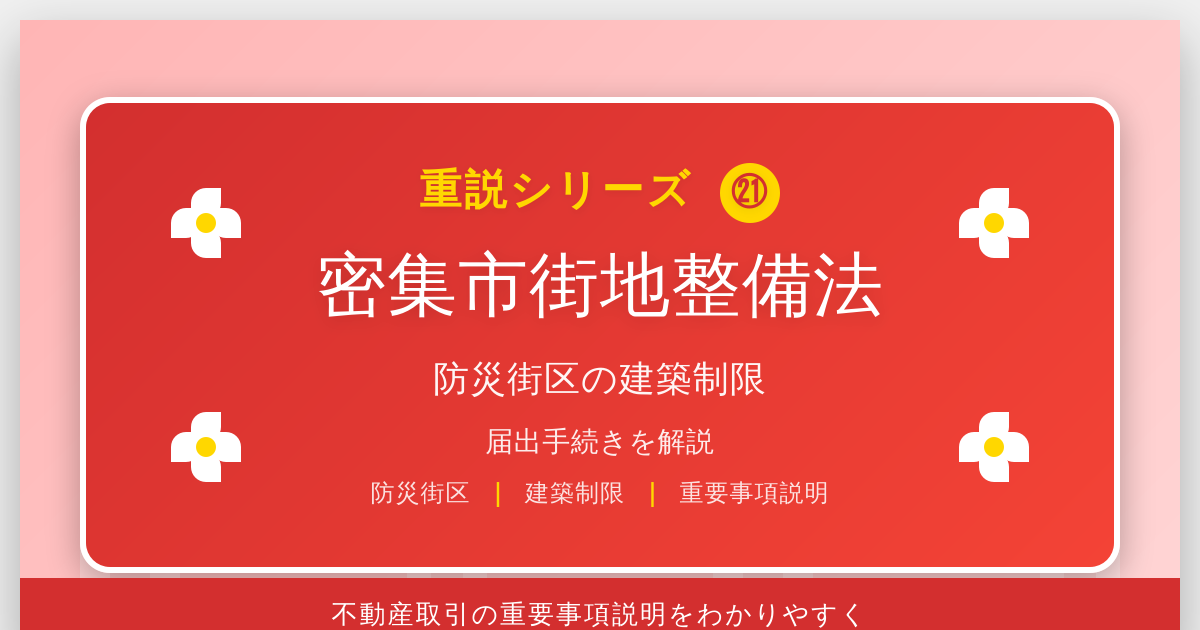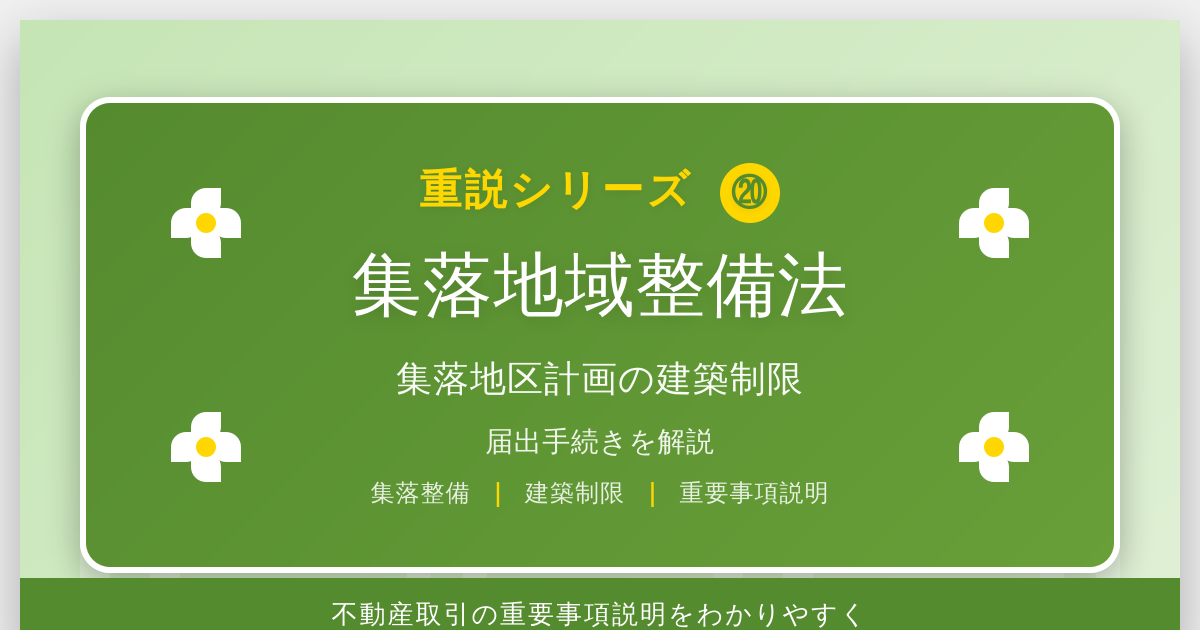大都市法とは?住宅街区整備事業と建築制限をわかりやすく解説|重説シリーズ⑨

大都市法(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)を徹底解説。住宅街区整備事業の仕組み、建築制限、重要事項説明のポイントを初心者にもわかりやすく図解付きで説明します。
📑 目次
大都市法とは?住宅街区整備事業と建築制限をわかりやすく解説|重説シリーズ⑨
❓ 「大都市法」って、普通の都市計画法と何が違うの?
❓ 東京や大阪だけで適用される特別なルールがあるって本当?
❓ 「住宅街区整備事業」の区域内だと、何に注意すべき?
通称「大都市法」は、その名の通り、東京・大阪・名古屋の**三大都市圏**において、**住宅地やマンションの供給をスピーディーに進める**ための特別な法律です。前回の「土地区画整理法」のパワーアップ版とも言える内容で、特に「住宅街区整備事業」は重説で重要なポイントです。
🏙️ 法律の目的と役割:大都市に住宅を増やす
この法律の正式名称は「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」です。1975年(昭和50年)に制定されました。
背景には、大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)への急速な人口集中に対し、住宅地や住宅の供給が追いつかないという問題がありました。この法律は、通常の都市計画法や土地区画整理法だけでは対応が難しい大都市圏特有の課題を解決し、**「大量の住宅・住宅地」を「迅速に」供給する**ことを目的としています。
大都市法の主な目的
- 大都市圏への住宅・住宅地の大量供給
- 良好な住宅街区の整備(特にマンションなどの共同住宅)
- 土地区画整理事業などの開発事業を促進するための**特別な措置**
🏘️ 大都市法の2つの主要制度
この法律が定める事業のうち、不動産取引の重要事項説明で特に登場するのが、以下の2つの制度です。
1. 土地区画整理促進区域(法第7条)
これは、大都市圏の市街化区域内で、良好な住宅地をスピーディーに供給するために「特に土地区画整理事業を促進すべき」と指定されるエリアです。
この区域に指定されると、建築行為などに**「許可」**が必要になります。これは、無秩序な開発が始まる前に事業計画を確定させるための、いわば「準備期間」の制限です。
⚠️ 届出(法第7条1項)が必要な行為
「土地区画整理促進区域」内では、以下の行為をする際に**都道府県知事等の許可**が必要です。
- 土地の形質の変更
- 建築物・工作物の新築、改築、増築
※これは、前回の土地区画整理法76条の制限に似ていますが、事業が「始まる前」の段階でかかる制限という点が異なります。
2. 住宅街区整備事業(法第26条, 第67条, 第83条)
こちらが**大都市法のメイン**となる制度です。通常の土地区画整理事業(土地の交換)と、市街地再開発事業(権利変換でビルを建てる)の「良いとこ取り」をしたような事業です。
簡単に言えば、**「土地を整備して交換する(換地)」**と**「共同住宅(マンション)を建設する」**を一体的に行う事業です。これにより、土地を整備するだけでなく、その上に住宅も同時に供給することができます。
(図解:「住宅街区整備事業」のイメージ。土地の交換と共同住宅の建設を同時に行う)
📑 住宅街区整備事業の3つの重要制限
「住宅街区整備事業」の区域内に土地(仮換地を含む)を持っている場合、不動産取引の重説では以下の3つの制限が説明されます。これは前回の「土地区画整理法」の制限とほぼ同じ内容です。
1. 促進区域内の建築制限(法第26条1項)
「住宅街区整備促進区域」に指定されると、無秩序な開発を防ぐため、建築行為等に都道府県知事等の**「許可」**が必要になります。これは事業が本格的に始まる前の準備段階の制限です。
2. 事業施行地区内の建築制限(法第67条1項)
事業計画が認可され、事業がスタートすると、より厳しい建築制限がかかります。これは土地区画整理法の「76条許可」と同じものです。
事業の完了(換地処分の公告)まで、事業の障害となる以下の行為は、都道府県知事等の**「許可」**がなければ行えません。
- 土地の形質の変更
- 建築物・工作物の新築、改築、増築
- 5トンを超える物件の設置・堆積
3. 仮換地指定と元の土地の使用停止(法第83条)
これも土地区画整理法(99条・100条)と全く同じルールです。
⚠️ 仮換地が指定されたら要注意!
「仮換地」が指定されると、元の土地(従前の宅地)は**使用・収益が「停止」**されます。登記簿上の所有者であっても、もうその土地は使えません。
代わりに、新しく指定された「仮換地」を使用する権利を得ます。家を建てたり、売買したりする対象は、この「仮換地」になります。
📊 比較表:「通常の土地区画整理」と「住宅街区整備事業」
| 項目 | ① 通常の土地区画整理事業 (前回の復習) |
② 住宅街区整備事業 (今回の大都市法) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 道路や公園の整備、 宅地の利用効率アップ |
宅地整備 + 共同住宅(マンション)の供給 |
| 主な手法 | 換地(土地と土地の交換) | 換地 + 共同住宅の建設 |
| 成果物 | 整備された「土地(換地)」 | 整備された「土地(換地)」 または 「共同住宅の床+土地持分」 |
| 適用エリア | 全国の都市計画区域内 | 三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)のみ |
✅ 重要事項説明での扱いとチェックポイント
取引する土地が「大都市法」の区域内にある場合、宅地建物取引業者はその内容を重要事項説明(重説)で買主に説明する義務があります。
1. 重説で説明される項目
重説では、主に以下の点が説明されます。
- 法律名: 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
- 区域の指定:
- 「土地区画整理促進区域」(法第7条1項)
- 「住宅街区整備促進区域」(法第26条1項)
- 事業中の制限:
- 「住宅街区整備事業」の施行地区である場合、建築等に**許可**が必要であること(法第67条1項)。
- 仮換地の状況:
- 「仮換地」が指定されている場合、元の土地(従前の宅地)の**使用収益が停止**していること(法第83条)。
2. 買主・仲介業者のチェックポイント
新人営業マンや買主様は、土地区画整理法とほぼ同じ点に注意します。
大都市法 取引チェックポイント
- ① 「何の事業」が「どの段階」か?
「土地区画整理促進区域」や「住宅街区整備促進区域」の段階(事業準備中)なのか、既に「事業施行地区」(事業中)なのかを確認します。 - ② 建築制限(67条許可)はいつまでか?
事業中の場合、完了(換地処分の公告)まで建築・増改築に許可が必要です。 - ③ 実際に使う土地は「仮換地」か?
仮換地が指定済みの場合、売買の対象は登記簿上の「従前の宅地」ですが、実際に使用・建築するのは「仮換地」であることを明確に区別します。
❓ FAQ(よくある質問と回答)
Q1: 大都市法は、福岡や札幌でも適用されますか?
A1: いいえ、適用されません。この法律は、その名の通り「大都市地域」、具体的には**首都圏、近畿圏、中部圏**の政令で定められた区域(主に市街化区域)に限定して適用される特別な法律です。
Q2: 結局、「住宅街区整備事業」と「土地区画整理事業」の一番の違いは何ですか?
A2: 一番の違いは、**「共同住宅(マンション)を建てることが事業の目的に含まれている」**点です。通常の土地区画整理は土地をキレイに整地するのがゴールですが、住宅街区整備事業は、土地を整地した上で、その土地の権利(床)を持つマンションも一緒に建ててしまう事業です。
Q3: 「促進区域」(法7条や26条)の許可と、「事業施行地区」(法67条)の許可はどう違うのですか?
A3: かかるタイミングが違います。
・「促進区域」の許可(法7条, 26条) → 事業が「始まる前」の段階です。「これから事業を計画するから、変な建物を建てて邪魔しないでください」という制限です。
・「事業施行地区」の許可(法67条) → 事業が「スタートした後」の制限です。「今まさに工事中だから、障害になる建物は許可しません」という、より強力な制限です。
Q4: 住宅街区整備事業で、元の土地(一戸建て)がマンションの権利に変わることはありますか?
A4: あります。それがこの事業の特徴です。土地所有者が希望し、事業計画で「共同住宅区」として定められた場合、元の土地(従前の宅地)の権利は、新しく建設されるマンションの「床(専有部分)」と「敷地利用権(持分)」に交換(換地)されます。
まとめ
「大都市法」は、三大都市圏において、土地区画整理と住宅供給を一体的に進めるための法律です。不動産取引においては、前回の「土地区画整理法」の知識がそのまま役立ちます。
🔑 大都市法における重要ポイント
- 三大都市圏限定の法律である。
- 主な制度は「土地区画整理促進区域」と**「住宅街区整備事業」**の2つ。
- 住宅街区整備事業は、土地の交換(換地)とマンション建設を同時に行う。
- 事業中は「建築許可(67条)」が必要で、「仮換地」が指定されると**元の土地は使えなくなる**。
売買・仲介に携わる宅地建物取引業者は、その土地が土地区画整理法なのか、大都市法なのかを区別し、特に「住宅街区整備事業」の場合は、将来の権利が「土地」になるのか「マンションの床」になるのかを、事業計画書などで正確に調査し説明する必要があります。
ご不安な不動産取引はオッティモにご相談ください
大都市法や土地区画整理事業地内の物件についてご不明な点がございましたら、不動産取引の専門家であるオッティモが承ります。お気軽にご連絡ください。
📞 電話で相談 (03-4503-6565) 💬 LINEで相談 (@466ktyjp) 💻 チャットで相談営業時間: 平日9:00〜18:00
❓ よくある質問(FAQ)
空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:
- 登記済権利証または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- 建物の図面や測量図
- 身分証明書
査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。