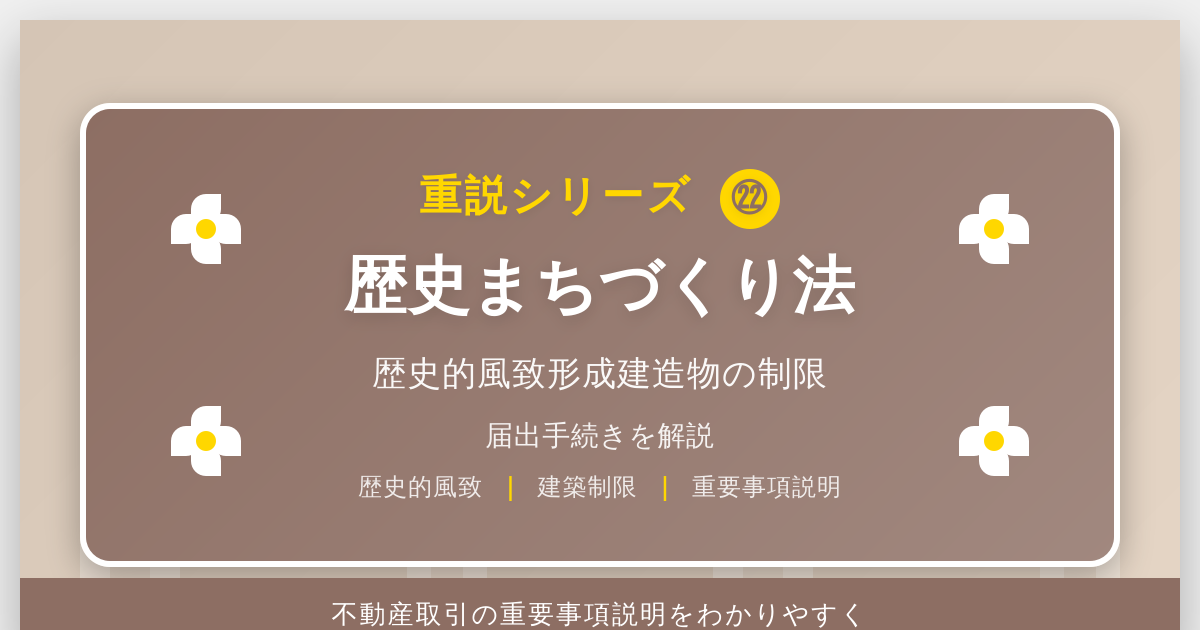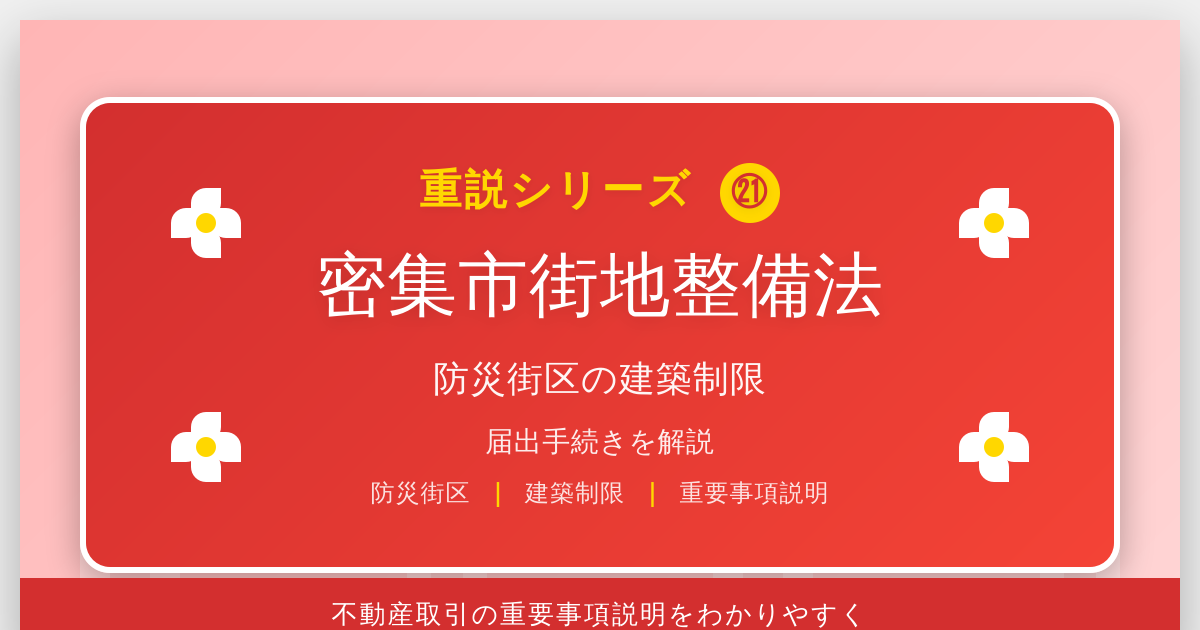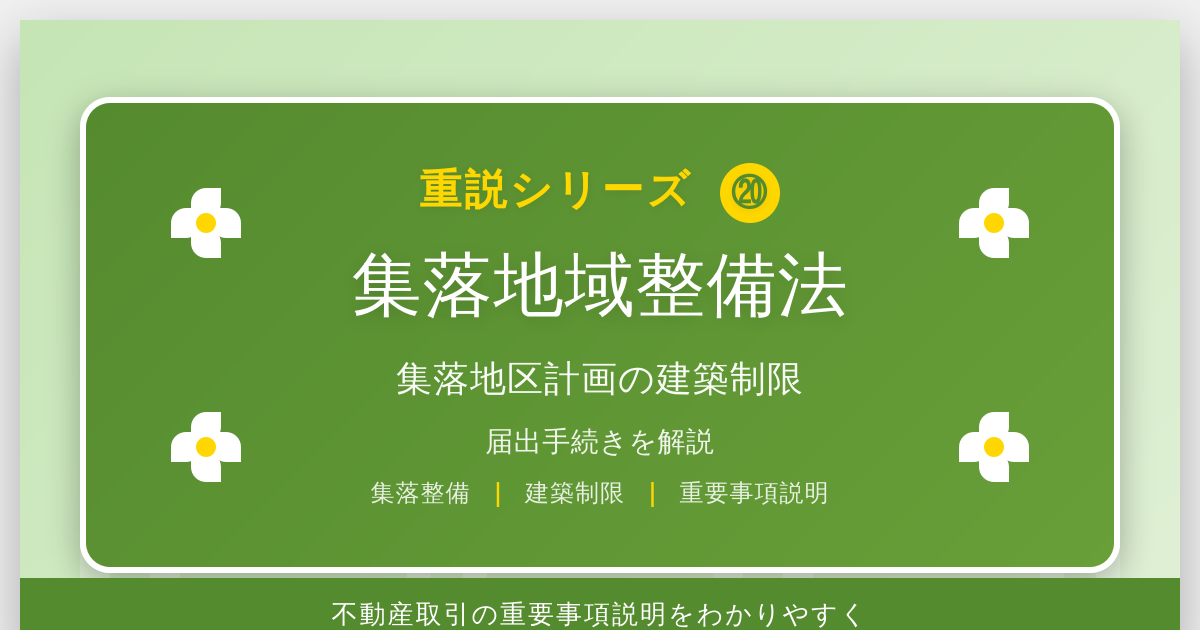旧市街地改造法とは?「防災建築街区」の建築制限を解説|重説シリーズ⑭
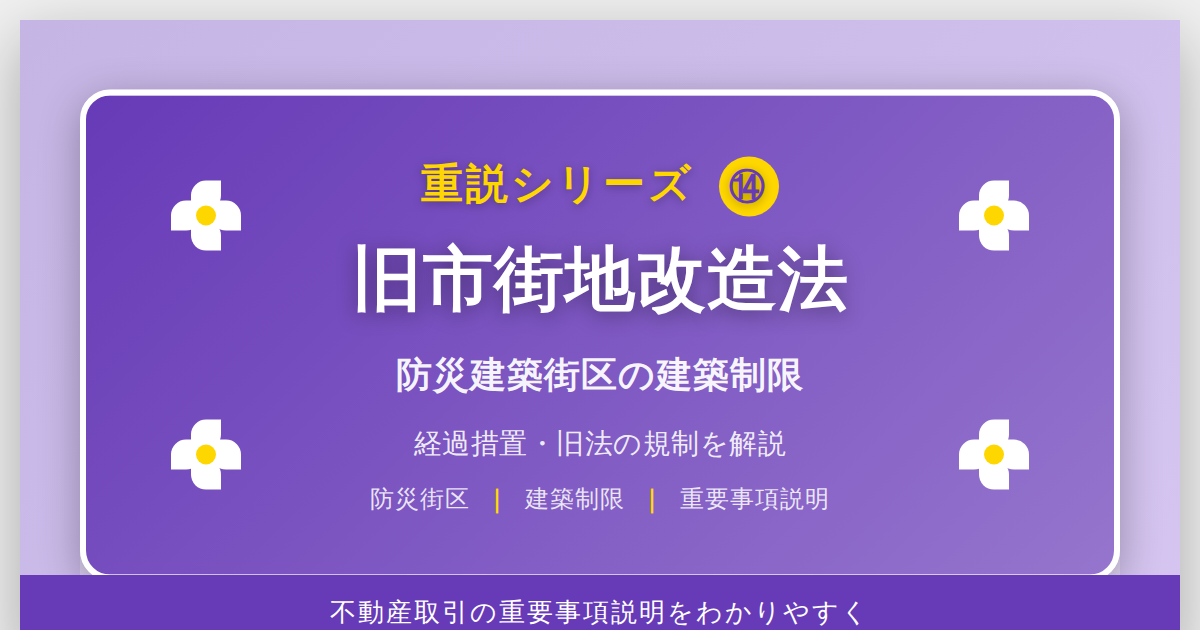
旧市街地改造法の「防災建築街区」と建築制限を徹底解説。防災街区の指定要件、建築物の制限内容、重要事項説明のポイントを初心者にもわかりやすく図解します。旧法の経過措置も解説。
📑 目次
旧市街地改造法とは?「防災建築街区」の建築制限を解説|重説シリーズ⑭
❓ 「旧」の法律なのに、なぜ今も重要事項説明に出てくるの?
❓ 「市街地改造法」って、何をするための法律だった?
❓ 「防災建築街区」に指定されると、何が制限される?
この法律は、1969年(昭和44年)に「都市再開発法」が制定されたことで、**すでに廃止された法律**です。しかし、廃止される前に開始された「市街地改造事業」のうち、**ごく一部がまだ完了していない**場合があります。その事業地内の不動産取引では、今もこの法律の制限(建築制限)が適用されるため、重説の対象となっています。
🏛️ 法律の目的と役割:戦後復興と防災街区の整備
「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(市街地改造法)」は、1961年(昭和36年)に制定されました。戦後の復興期において、公共施設(道路、広場など)の整備と、その周辺の市街地(特に防災上問題のある木造密集地など)を一体的に整備・改造することが目的でした。
この法律の主な役割は、現在の「都市再開発法」が担う役割の先駆けであり、特に「防災建築街区造成事業」という手法を用いて、火災に強い街づくりを進めることでした。
(図解:市街地改造法から都市再開発法への変遷)
この法律のポイント
- 現在は**廃止**されており、新規に指定されることはありません。
- 「都市再開発法」がこの法律の役割を引き継いでいます。
- ただし、廃止当時に**「現に施行中」だった事業**については、完了するまでこの法律が適用されます(これを「経過措置」といいます)。
🏘️ 重説の最重要ポイント「防災建築街区造成事業」(法第13条)
重要事項説明で唯一説明の対象となるのが、この法律の廃止前から続く**「防災建築街区造成事業」**の施行地区内における建築制限です。
1. 「防災建築街区造成事業」とは?
この事業は、主に「災害危険区域」や「防火地域」に指定された木造密集地などで、道路などの公共施設を整備しつつ、周辺の建物を**耐火建築物や準耐火建築物**(=防災建築物)に建て替えさせる事業です。
これにより、火災に強い安全な街区(街ブロック)を造成(つくりだす)ことを目指しました。
(図解:「防災建築街区造成事業」のビフォー・アフター)
2. どんな制限がかかる?(法第13条)
この「防災建築街区造成事業」の**施行地区内**に指定されると、事業が完了するまでの間、事業の障害となるおそれがある行為は厳しく制限されます。
区域内で以下の行為をしようとする者は、原則として**国土交通大臣または都道府県知事の「許可」**が必要になります。
⚠️ 知事等の「許可」が必要な行為(法13条)
これは、現在廃止されている「防災建築街区造成法」の第55条1項を準用する形となっています。
- 土地の形質の変更(切土、盛土、造成など)
- 建築物・工作物の新築、改築、増築
※この制限は、土地区画整理法第76条や都市再開発法第66条の制限とほぼ同じ内容です。事業が進行中であるため、計画の妨げになる建築は許可されません。
✅ 重要事項説明での扱いとチェックポイント
取引する土地が、この「旧市街地改造法」の施行地区内にある(=まだ事業が完了していない)場合、宅地建物取引業者はその内容を重要事項説明(重説)で買主に説明する義務があります。
1. 重説で説明される項目
重説では、主に以下の点が説明されます。
- 法律名: 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律 第13条1項
- 区域の指定: 当該土地が「防災建築街区造成事業」の施行地区内にある旨。
- 制限の概要: 建築物の新築・改築・増築や土地の形質の変更には、**国土交通大臣または都道府県知事の「許可」**が必要であること。
2. 買主・仲介業者のチェックポイント
新人営業マンや買主様は、特に以下の点に注意して確認しましょう。
旧市街地改造法 取引チェックポイント
- ① 「旧法」だが「現役」の制限か?
この法律は廃止されていますが、取引対象の物件が「まだ完了していない事業地」に含まれていないか、行政の都市計画課や再開発担当課で確認が必須です。(該当するケースは極めて稀です) - ② 建築制限(許可制)の存在
もし該当した場合、その土地では事業が完了するまで建築や増改築に「許可」が必要です。買主が建築を予定している場合、事業の妨げになると判断されれば許可が下りないリスクを説明します。 - ③ 事業の完了予定はいつか?
万が一、このような稀な物件に遭遇した場合、施行者(行政など)に対して、事業がいつ完了し、建築制限が解除される見込みなのかを確認することが重要です。
❓ FAQ(よくある質問と回答)
Q1: なぜ「旧」の法律が、今も重説の対象なのですか?
A1: 法律が廃止されても、廃止前から始まっていた事業は、原則として当時の法律(旧法)に基づいて進められるためです。1969年に法律が廃止されてから50年以上経過しているため、ほとんどの事業は完了していますが、万が一にも完了していない事業地が存在する場合に備え、重説の対象として残されています。
Q2: 「防災建築街区造成事業」と、今の「市街地再開発事業」はどう違うのですか?
A2: 目的(防災性の高い街づくり)は似ていますが、手法が異なります。「防災建築街区造成事業」は、主に耐火建築物を建てることを主眼とした、比較的シンプルな開発手法でした。一方、現在の「市街地再開発事業」(都市再開発法)は、「権利変換」という手法を用いて、元の権利者が新しい再開発ビルの床(マンションや店舗)を取得するなど、より複雑で高度な権利調整を行うことができます。
Q3: 現代の不動産取引で、この法律に遭遇する可能性はありますか?
A3: **可能性は極めて低い**です。ほとんどの事業は既に完了し、「都市再開発法」に基づく事業に移行しています。しかし、法律(宅地建物取引業法施行令)の条文として現存する以上、宅建業者は「該当しない」ことを確認する義務があり、そのために重説の項目として残っています。
Q4: もし該当した場合、建築の許可は下りますか?
A4: 事業の最終段階であれば許可が下りる可能性もありますが、事業の障害になると判断されれば不許可となります。これは土地区画整理法76条許可と同様に、事業の円滑な進行を最優先するための制限だからです。
まとめ
「旧市街地改造法」は、現在は廃止された法律ですが、万が一、廃止前から続く「防災建築街区造成事業」が完了していない区域では、今もなお建築制限が適用されます。
🔑 旧市街地改造法における重要ポイント
- 現在は廃止されており、新規指定はない。
- 廃止前から続く**「防災建築街区造成事業」**の施行地区内のみが重説の対象。
- 該当地区内では、事業完了まで建築や造成に**「許可」**が必要(法第13条)。
- 実務で遭遇する可能性は極めて低いが、調査は必須。
売買・仲介に携わる宅地建物取引業者は、このような「旧法」に基づく制限が(ごく稀に)存在することも念頭に置き、行政調査を徹底することが求められます。
ご不安な不動産取引はオッティモにご相談ください
古い法律に基づく制限や、再開発区域内の不動産取引についてご不明な点がございましたら、不動産取引の専門家であるオッティモが承ります。お気軽にご連絡ください。
📞 電話で相談 (03-4503-6565) 💬 LINEで相談 (@466ktyjp) 💻 チャットで相談営業時間: 平日9:00〜18:00
❓ よくある質問(FAQ)
空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:
- 登記済権利証または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- 建物の図面や測量図
- 身分証明書
査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。